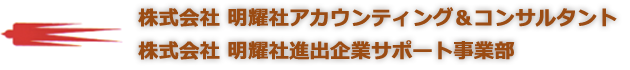タイ国の税務については個別案件を挙げ解説したことがある筈だが、今稿ではもう少し踏み込んで、税務調査の前提としての考え方、という様な課題で述べてみたい。
日本での税務調査は税務官が納税者を訪問し必要書類やデータの閲覧を要求し、損金否認を求めるための材料を照合・証明し、経営者に対し理詰めの追及を行う。つまり当局の側に立証義務がある。
しかしこれがタイでは逆転する。抜き打ちの訪問も無いことは無いが一般的には、先ず「これこれの証憑とデータを取り揃え、何月何日何時に出頭する様」との出頭要請が郵便送付される。
調査は、定期(場合により不定期)的な一般調査の場合と、付加価値税や所得税の還付請求に応じて行う調査(つまり払い戻す金額をできるだけ減額しあるいはゼロやマイナスにするのが目的)の2種類がある。業種にもよるが、特に輸出がメインの企業である場合には、輸出の際に発生する付加価値税が0%である為、還付申請が必須となる。これを行わねば購買や費用支払いの際に支払った付加価値税が未還付分として蓄積するばかりになるからである。逆に国内販売がメインならば、仕入および費用支払いの際に支払った付加価値税は国内販売の売上で生じる付加価値税と相殺されるのでこの手続きは不要である。
そして管轄税務署に出頭すると、当然のことながら税務官は指摘事項を(多くの場合数年間の決算書と申告書から抽出した“叩けばホコリの出そうな案件を”)準備して待ち構えている。
さて、ここからが日本との大きな違いだ。当たり前だが納税者側は都合の悪いデータやエビデンスを持参せず、都合の良い言い訳をするのみ。これでは調査が進まない。
そこでタイ税務官の伝家の宝刀「推定課税」に向け厳しい追及を受ける訳だ。当地では税務官の推定課税が大きく認められている。実際にはまだまだ弁明の機会は与えられるのだが、例えばこれこれの費用に関し、業務関連性を証明するエビデンスがあれば追加提出せよ、という指示が与えられ、納税者側は一旦帰社し、後日求められたデータを(あればの話)再度提出する。場合によってはこれが何度も繰り返されるので、担当者の時間的負担は相当なものになるが、この過程で納税側は、追及された案件について「それは正しく処理され、具体的な業務関連性はこの通りである」との立証責任が求められるのだ。
やがて話し合いが煮詰まって来ると、「納税側が立証できなかった件」につき税務官から具体的な修正申告を試算した数値(ただし必ずと言っていいほど手書きのメモ、税務官自身が一切ミスを追求されぬ様、証拠は残さない)が提示され、「今回はこの様な試算をしてみたが、これだけの修正申告、納税をしてはどうか」と決まり文句を聞かされる。次の句も予定通り「認めなければ改めて専門調査チームが訪問の上、隅から隅まで調査させていただく」という殺し文句である。
しかしタイ納税者もあっさりとは引き下がらない。ここで「ははー!お代官様には逆らえやせん」と素直にお白洲の土に手をついてしまっては当の代官も「これは組みし易し」と、取り易い納税者リストに記帳され、毎年毎年キツイお取調べを仕掛けてくるのは間違いない。。ここで賢い町民であれば、「お代官様、それはご無体な。こちとらただただ懸命に働いてめぇりやした町民風情でごぜぇやす。何卒、何卒お慈悲を~」ということであせらずじっくり条件闘争に臨むのである。
市場価格制に基づく(ただし税務側は市場データなど持っておらず、せいぜい同社の前年度実績と比較し利益率が落ちた、という程度の根拠)廉価販売だというのであれば売上高の修正から、原価調整による算出を提案し、せめて付加価値税の修正(これは罰則金が非常に大きいため)を除く法人所得税のみの修正という方法ではどうかという提案をしてみたり、日本人に係る給与・関連費用であれば2名分を1名分でご勘弁いただく。などの手練手管で粘り強く交渉をすべきだ。税務官側の論拠も極めて大雑把なものであるし、彼らの側にも所要時間(費用)対徴税額(効果)の観念はあるから、十分に交渉する余地はある。ただし当管轄税務署の、または当税務官の徴税ノルマや、税務官の性格にもよるので、当然その結末もケース・バイ・ケースということになる。ここは微笑みの国、にこやかにしたたかに交渉に臨んでいただきたい。