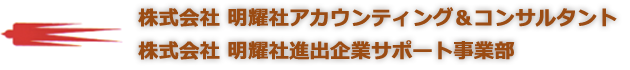法人として申告納税上の日本との大きな相違は、第一にVAT(付加価値税)を毎月申告納税すること、源泉徴収対象の多さ、また法人所得税に関しては、損金計上できる費用の範囲が狭いことである。
今回はこの3テーマについて概要を述べよう。
1 まずVAT(Value Added Tax、付加価値税、日本の消費税に近い)について、法人がVAT登録企業である場合、これはほぼすべての企業(年間収益が180万バーツ未満であれば対象外)が対象となる。ただし教育・出版・医療、あるいは100%生鮮品はVAT課税の対象外であり、これに伴いその企業は仕入や費用でVATを支払っても還付対象外である。
当月のVATは翌月の15日までに算出、申告を行い、納税分があれば申告と同時に納税する。ここで押さえておくべきは、この毎月の申告が確定申告であること、またこの申告が同時に各企業の収益額の報告も兼ねているため、税務当局にとしては、企業間の取引・金銭の流れをほぼすべて把握し取引データを入手することが、税収を上げるための有効な制度となっている。確定申告であるから、申告漏れや申告遅延、あるいは不正還付請求は直接、罰則金の対象となり、正確な税計算が求められるところである。
また、もう一つ認識しておくべきことはVATの負担者は最終消費者であって、法人が中間取引者である場合、VATの税負担はないということ。まず仕入れ時にパーチャス(購買)VATを支払うが、この額は申告時に還付分として加算される。また、販売時に受け取るセールス(販売)VATは、申告時に納税分に加算される。この両者、つまりパーチャスVATとセールスVATと相殺の結果、納税分が上回る場合に納税し、還付分が多い場合にはデビットとして翌月に繰越すか、または当月度分までの還付請求を行う。
還付される次期については以前に比較しかなり迅速化されてはいるが、還付前の税務調査は厳しく行われている。各管轄税務署には、独立した法人所得税およびVATの還付前調査チームが必ずある。輸出が中心の企業などでは輸出品に対するVAT税率が0%であることから、還付分が増加する一方となり還付請求を行わない訳にはいかないが、国内販売が中心の企業であれば月次申告上、相殺を継続してゆけば、余計な税務調査を受ける必要はない。
2 源泉徴収についてだが、先ず源泉徴収義務対象の範囲が非常に広いことが挙げられる。例を挙げれば、請負サービス、コミッション、賃貸料、広告費、海外への利益送金、製造販売であっても量産品で無く受注生産品の販売に対する支払いは源泉徴収の対象となる。元より源泉徴収とは税徴収の業務を法人に移転し、徴収漏れを防ぐという税務側の意図により制度化されたものだ。タイのビジネス文化の中で、納税意識の低さということも関係しているだろう。
源泉徴収税について理解しにくい点は、源泉徴収義務者と税負担者が別である、ということだ。例えばサービス料等を支払う際、支払者が源泉徴収義務者(支払金額から源泉分を差し引いて支払い、その額を翌月7日までに申告納税する)となる。従って実際の税負担者は源泉分を差し引かれた対価を受け取った側だということになる。源泉徴収税であるから、この税負担者は税額票を保管し、確定申告の際に前払法人所得税として控除できる。
また源泉徴収義務者がこれを怠ると、源泉徴収義務違反として税負担を肩代りしなければならないという制度になっているため、これも業務上常に注意すべきことの一つである。
併せ問題となるのは確定申告の際に赤字申告であったり、つまりこれは相殺をする相手である法人所得税の納税が生じない場合、あるいは業務の性質上、必ず前払源泉徴収分が法人所得税額より上回る業種もあり、支払超となってしまうケースがある。
こういったケースでは制度上還付請求を行うべきだが、還付を行う際には非常に厳しい税務調査が行われるため、請求を行う納税者側が、常に正しい会計・税務を行っているという自信を持っていないと、藪蛇となってしまう結果が予想されることもあり得るので、これについても慎重に考えなければならない。次の項で説明する法人所得税でもポイントとなる「費用の厳正な業務関連性」を考慮する必要がある。(その2へ続く)