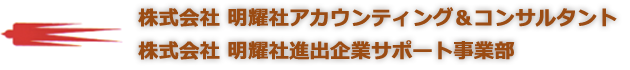1997年に発生した通貨危機後の財政健全化と、それでも尚衰えるない直接投資に適応するため「2000年会計法」が制定・施行された。
当会計法上、すでに批准している国際会計基準に沿い、様々な会計上、税務上の新基準が採用されている。法人税に関しては、親子会社や関連会社間取引における利益調整を規制するための移転価格税制、さらに徴税適正化を図り廉価販売を規制する市場価格制などが主なものだ。ただ後者についてはグローバル化推進を大義名分として拡大解釈し、税務官の推定課税権を最大限利用しているという批判がある。また個人所得税関連での大きな変化は、合算申告である。
当地にカレンダー年の内180日間以上滞在した者はタイ居住者と見做され、日本を含めた海外で得た全所得を合算し当地で申告納税し、その記録(納税証明書)を以て他国での申告を行わなければならない、という規定である。ただし日本の給与所得者は年末調整で事足りることから、多くの対象納税者は海外転出時に住民票の転出届を行い、それ以降は源泉徴収を行わないという方法を選択すると思われる。日タイ間では二重課税防止協定により、支払超過分があれば還付請求は可能である。
当時税務当局は、数年内にすべての外国系企業に調査をかける、各企業の業種業態・規模・役職により、税務署が調査をした給与水準により推定課税も可能、としていた。しかし実際にはその様な実態調査を行う人的余裕はなく、一般税務調査の際にインタビューを行い、税務官も「所得の内タイに持ち込んだ額を加算し修正申告をしたらどうか」という程度のものであった。
ところが数か月前より事態は一変したのである。
調査のターゲットと定めた人物の、日本での所得申告内容を税務署間で問い合わせ、日本側も数日以内に公文書として回答してくるという協力体制が構築されていたのである。この場合は当然、推定課税に対する交渉の余地はなく、申告漏れがあれば有無を言わさず脱税として取り扱われる。追徴税額に罰則金、数年間の延滞金(1.5%/月)が加算され、納税者によってはひと財産と云えるほどの金額が徴収された。特にこのケースでは、日本側では非居住者として源泉徴収を行わず、タイ側では合算を怠っていたため、最悪の結果となった。日本で納税がされているケースでは、合算した総所得と、それぞれの申告額との差額が問題にされる。日本の所得控除もタイ側では考慮されないため一般的にそれなりの金額になる。
こういった事例はここタイだけの話ではなく、在インド日系法人でも同様の事例があったそうなので、全世界的に税務当局のネットワーク化が進んでいる可能性がある。
多くの日本企業が海外拠点に軸足を移してゆく昨今、すでに日本の税務当局も在外法人に関わる費用、特に長期出張者の給与、そして海外への直接投資に対する利益還元を重要調査項目としており、会計税務においても国境というハードルが無くなる時代へと変化が始まっている。
この様な時代には、当然のことながら海外業務の経験が皆無の企業が海外進出という選択肢を迫られるケースが多々ある中で、経営者は更なる緊張感、慎重な判断を迫られる。云うまでもなく、海外へ出れば我々は外国人、全くのアウェイ・チームであると認識される方が良い。